
こんにちは、行政書士の野口です。
今回は死後事務委任契約を検討する上で、非常に重要な葬儀の種類について触れさせていただきます。
■死後事務委任契約について
最近では終活ブームも手伝って、自身がお亡くなりになる前に身の回りを整理しておくという風潮が高まっているようです。
更には葬儀の方法や、納骨までも先に決めておくなど、ご自身の希望通りの設定をされている方も少なくないと聞いております。
終活は少子高齢化社会が後押しするように、メディアなどでも扱われることで、多くの方に備えについて考える機会を与える要因になっている感じがします。
しかしながら同時に、少子高齢化が進んでいることで、様々な問題が表面化してきております。
一人暮らしの高齢者の増加もその一例だと考えられますが、令和7年においては、男性で290万人、女性で525万人、全体で815万人であり、2000年の全体で300万人程度と比較すると着実に、そして急激に増加していることが伺われます。
これは65歳以上の高齢者の割合で、男性で5.5人に一人、女性で4人に一人が一人暮らしをされているということになります。
お一人で暮らされている方には、各々で理由があるかと思います。
既に配偶者や親族と死別された方や、子供や親族は疎遠になられている方などもいらっしゃると考えられますが、そのような環境の方が終活を検討する際には、「一人暮らしの人が亡くなったら、誰が葬儀などをしてくれるのだろう?」といった疑問が出るのではないでしょうか。
そのような問題を解消する為に、近年では、ご自身が亡くなった後に発生する様々な手続きについて、第三者に委任する「死後事務委任契約」が注目されてきております。
死後事務委任契約の詳細につきましては別ブログにて紹介させていただいておりますのでそちらをご参照いただければ幸いです。
参照:『誰に必要? 死後事務委任契約で“安心できる人”とは』
今回のブログでは、死後事務委任契約を設定する上で、必ず検討しなければならない一つとして、葬儀の仕方について解説させていただきます。
葬儀そのものに関しては、多くの方が当然ご承知かと思いますが、葬儀の実態については、なかなか詳細までご存じという方は少ないのではないでしょうか?
葬儀に詳しくなるまで、頻繁に身近な方が亡くなるなんてことは、あまり考えたくないですよね。
私自身、死後事務委任契約を学ぶことで、葬儀や納骨などについて、多くのことを知り得たと思います。
葬儀の種類は、参列者の人数や宗教、儀式の簡略度などで様々な分類方法がありますが、多くは、一般葬、家族葬、直葬(火葬式)が主な形態として分けることが出来ます。
■直葬(火葬式)
通夜や告別式などの宗教的な儀式を行わず、ご遺体を火葬のみで弔う葬送スタイルです。
ただ、例えば病院で亡くなられた直後に火葬場に搬送するということは出来ません。
お亡くなりになったら、まず死亡届を役所に提出して、火葬許可を得る必要があります。
その火葬許可を基に火葬場に予約を入れることになります。
そして予約をしたとしても、数日待たされる、なんてことも考えられます。
その間、ご遺体の安置場所の確保や、搬送方法、ドライアイスの利用などが発生しますので、予算を含め、様々な点を考慮する必要があります。
それでも、最もシンプルで費用も抑えられる特徴から、お一人で暮らされてる方においては選択されるケースが多いようです。
一方で、親族や菩提寺の理解が必要となるほか、後日に弔問客が訪れることが出来ない、といったデメリットもありますので、選択される際はご検討いただく必要があります。
直葬のメリット
・葬儀にかかる費用を他の方法と比較して、大幅に削減できます。
・全体的に最小限の対応となるため、遺族の精神的負担が軽くなります。
・儀式自体が短時間で済むため、時間や手間がかかりません。
直葬のデメリット
・簡易的な対応のみに抵抗を感じる親族がいる場合があります。
・菩提寺によっては直葬を許可しない場合がありますので、事前に相談が必要です。
・訃報を知った友人や遠い親戚が、後から弔問に訪れる可能性があります。
・一般的な葬儀に比べて、お別れをする時間が短くなります。
■家族葬
家族葬は、コロナ禍以降において主流となっているようです。
家族葬とは、家族のみで執り行う小規模な葬儀となります。ただ家族といっても、配偶者のみである場合や、独立されたお子さん家族もご一緒の場合、又は地域によっては、親戚まで参列をしていただくことまでを家族葬と表現したりします。
その為、実際にどこまでの対応が可能となるか、該当する葬儀社とは事前の確認が必要となります。
いずれにせよ。参列者を親しい方々に限定することで、一般葬よりも落ち着いた雰囲気の中で故人と向き合い、心ゆくまでお別れができる点が特徴となります。
家族葬のメリット
・故人と直接の関わりが少ない人々を呼ぶことなく、家族や親族に絞って行われます。
・小規模な会場で執り行われることから、葬儀予算の軽減に繋がります。
・参列者への対応が少なく、静かな環境で故人との時間を過ごせます。
家族葬のデメリット
・参列者が少ないため、飲食接待費などが抑えられますが、香典などが期待できません。
・生前の交友関係のある方が故人を偲ぶことができない場合も考えられます。
■一般葬
一般葬は、従来執り行われていた葬儀方法で、故人の親族だけでなく、友人、知人、職場関係者、近所の方など、故人と関係があった人々を広く招いて行う葬儀スタイルとなります。
通夜と告別式を基本として行われ、参列者は香典や供花を供え、会食なども参列者に提供され、故人を偲ぶ方式をとります。
大規模で執り行われることが多く、費用も高額になりやすいですが、多くの方に故人を見送ってもらえるというメリットがあります。
コロナ禍以降では少なくなっているようですが、それなりの地位を持たれている方の場合や、故人の希望などから執り行われているようです。
一般葬のメリット
・生前の交友関係を尊重し、多くの関係者が故人を偲ぶことができます。
・葬儀当日に多くの関係者が弔問されるため、後日の弔問対応が軽減されます。
・故人と縁のある人々が一同に会すことで、故人の社会的なつながりを示せます。
一般葬のデメリット
・参列者が多い分、会場費、飲食費、返礼品代などが高額になります。
・参列者への対応が発生することで遺族の負担が大きくなることがあります。
・通夜の対応から告別式まで多くの時間が必要となります。
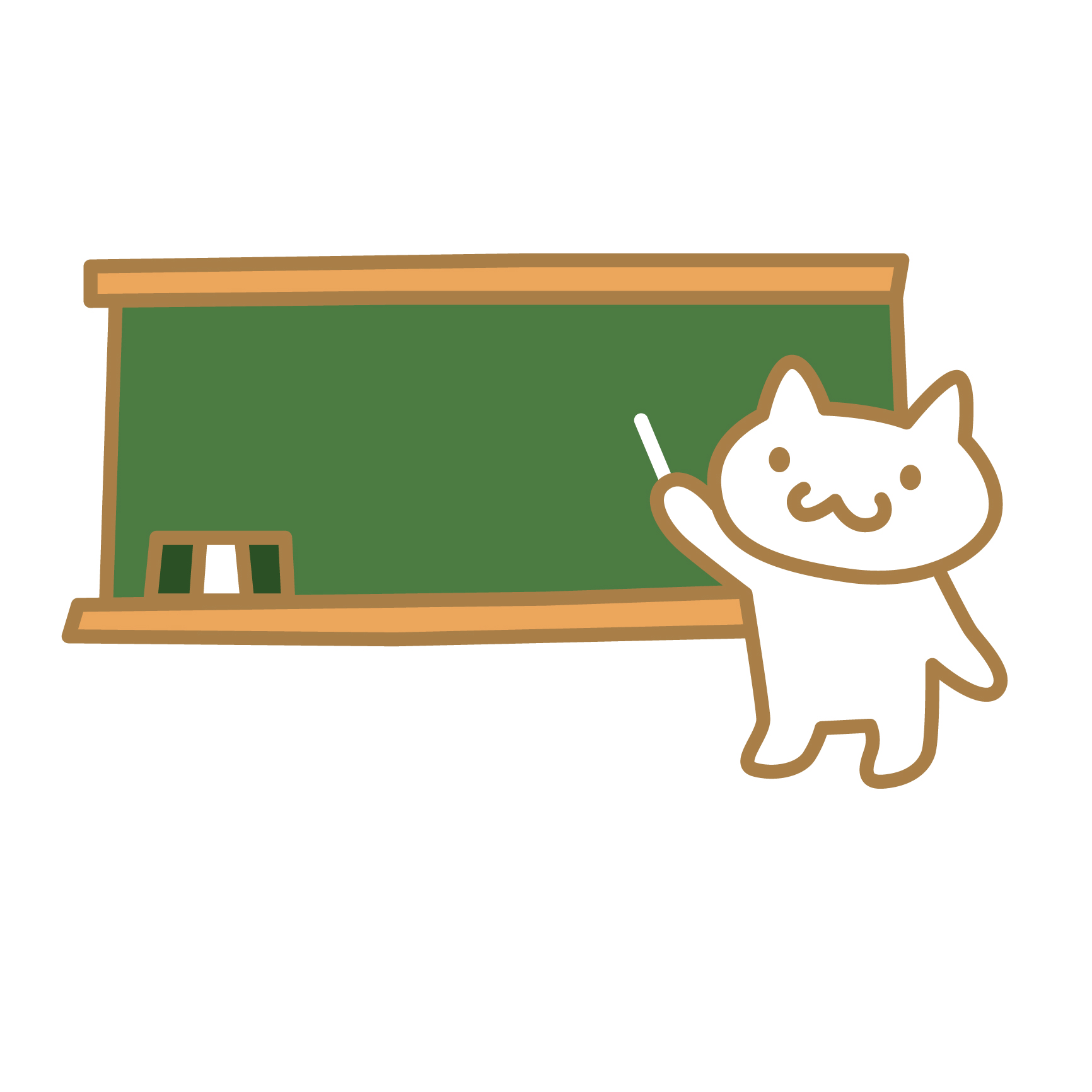
今回は死後事務委任契約を検討する上で、重要な手続きとなる葬儀の仕方について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。
葬儀は法律での決まりはなく、葬儀社と当事者との取決めによって行われることになります。死後事務委任契約を締結する際には重要事項の一つとなりますので、様々な情報を基にご検討されることをお勧めいたします。
死後事務委任契約につきましてご質問等ございましたら、お気軽当事務所までご相談ください。
👇無料相談のお問合せはこちらから!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ