
こんにちは、行政書士の野口です。
今回は相続財産を管理する手法として注目されている家族信託について触れさせていただきます。
■信託法の歴史
信託法
(定義)
第二条この法律において「信託」とは、次条各号に掲げる方法のいずれかにより、特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。同条において同じ。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいう。
3この法律において「信託財産」とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいう。
4この法律において「委託者」とは、次条各号に掲げる方法により信託をする者をいう。
5この法律において「受託者」とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
6この法律において「受益者」とは、受益権を有する者をいう。
7この法律において「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。
信託法の起源は古く、中世のイギリスから発祥したと言われております。
その当時は亡くなった後に、自分の土地を教会に寄付する慣習がありましたが、それでは税金が取れないという理由から法律で禁止されてしまったのです。
それに対抗する策として生まれたのが、信頼出来る方に自分の土地を譲り、そこから発生した収益を教会に寄付するという方法で、それが信託の始まりだそうです。
なんと十字軍の兵士も遠征の際に、信頼出来る友人に自分の財産を託して、家族の為に使ってもらったという歴史もあるそうで、古くから使われていた方策であることに非常に驚かされました。
その後、信託制度はアメリカに渡ることとなって、19世紀には信託を事業として行う会社がつくられます。そして、南北戦争によってインフラ関連の事業が盛んになったことを契機に、社債を引き受けて資金を提供するという形の信託会社が生まれたそうです。
日本への導入は明治時代の後半と言われております。
事業への信託を対象として発展した後、第一次世界大戦の好景気を境に多くの信託会社が生まれたそうです。戦争が契機というのはいつの時代も同じですね…
その後、信託制度の確立が必要とされることから法律における整備が必要となり、大正11年に「信託法」と「信託業法」が制定されることになりました。
■家族信託とは
家族信託は2006年の信託法改正により始まった契約形態であり、比較的新しいものになります。
それまでの信託制度では、信託業法の免許を持つ信託会社や信託銀行が営業として対応する商事信託の方法しか認められていませんでした。
それが2006年の信託法改正によって、一般の方においても信託制度を利用できる民事信託が認められ、更に家族間の相続対策や財産管理に利用されることから「家族信託」という呼称が生まれております。
家族信託(民事信託)の概要をお伝えしますと、各人が保有する財産の所有権を、「管理・処分する権限」と「財産としての価値」に分離して、信頼できる個人や法人に財産を管理・処分する権限を任せる(信託する)契約となります。
例えば、不動産や金融資産をお持ちの方が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、該当の資産は凍結されてしまい、成年後見の利用などが必要となり、柔軟な財産管理などが出来なくなってしまう恐れがあります。
家族信託は「凍結されて困る財産」を「凍結されないように備えておく手法」とお考えいただければ宜しいかと思います。
■家族信託の役割者
家族信託では各役割者を確定させて契約を締結する流れを取ります。
各役割者の詳細につきましては改めてご紹介させていただきますので今回はおおまかにお伝えします。
委 託 者 :財産の所有者であり、信託法における方法によって財産管理を託す人
受 託 者 :委託者より託された財産について、管理・運用・処分を行う義務を任された人
受 益 者 :信託された財産の管理・運用・処分によって利益を得る人(財産の権利を有する)
受益者代理人:代理する受益者の権利に関する裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する人
帰属権利者 :信託契約が終了、又は解除した時点で財産の受け取りを指定された人
信託監督人 :受益者のために受託者を監督する権限を有し、第三者が選任されるケースが多い
■家族信託の基本スタイル
家族信託では、家族関係や信託財産によって様々なスキームを設定することになります。
今回は基本となる形式につきましてご紹介させていただきます。
■自益信託
委託者と受益者が同一となる形式で、家族信託で最も利用頻度が高いスタイルとなります
財産の権利者は変わらない為、贈与税や相続税などの課税は生じません
■他益信託
当事者以外の第三者が利益を受ける形式で、認知症や障がい者が受益者となる場合が多いです
このケースでは受益権が委託者から受益者に移動する為、税務署への手続きが必要となります
■自立信託
委託者が受託者となり、自己の財産を管理する形式となります
会社経営における将来を見据えた後継者対策として利用されることがあります
■遺言信託
遺言書と同様の扱いで、委託者が死亡した時点から効力を発生させます
生前まではご自身で財産管理をしておきたいケースで利用されます
*銀行等で扱う「遺言信託」は商品名で、信託法に規定されているものとは異なります
参考:『家族信託はどう使う? 相続で役立つ仕組みと活かし方』
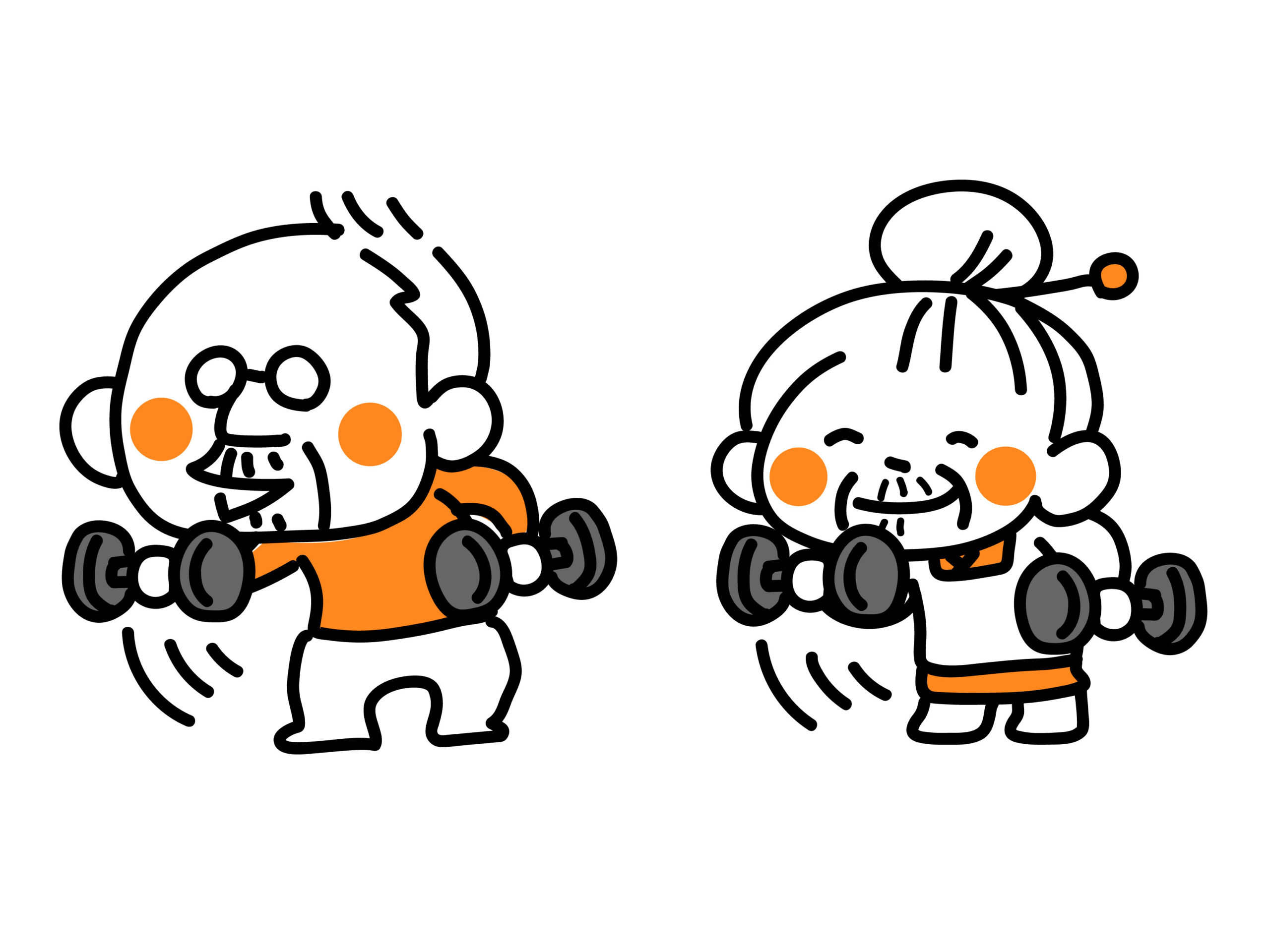
今回は家族信託について少しだけ触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。
家族信託は財産管理においてメリットが多く、とても使い易い手法の一つとされています。次回以降、契約形態やメリットなどについて深堀していきたいと思います。
家族信託における契約につきまして、詳細確認をご希望される場合は行政書士までお気軽にご相談いただければと存じます。
👇無料相談のお問合せはこちらから!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ