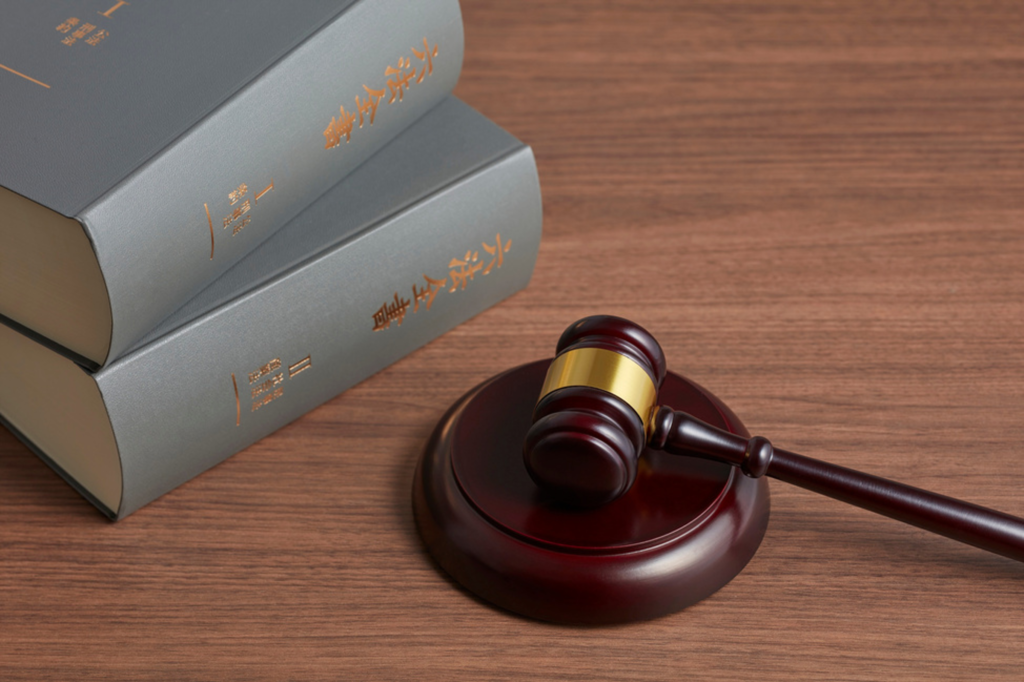
こんにちは、行政書士の野口です。
今回は任意後見契約を行うにあたって付随業務となる契約について触れさせていただきます。
■任意後見契約に関する法律
任意後見契約に関する法律
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一任意後見契約委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
平成11年に任意後見契約に関する法律が施行されました。
この法律は11条までしかない、非常にコンパクトな条文となっております。
そして、この条文には付随契約については全く触れられておりません。
しかしながら、任意後見契約を結ばれるのは判断能力が低下していない元気な方になりますので、任意後見契約が発するまでは契約自体が寝ている状態になっていることを考慮しないといけません。
それは別の見方をしますと、契約を発動させるタイミングを継続して確認していなければならないということに繋がります。
又、判断能力が低下した時点から、任意後見契約は本人が亡くなるまで業務は継続されます。
それでは、亡くなられた後はどうなるのでしょう?
もし入院していたら病院への精算や施設の支払などが発生しますし、他に身寄りの無い方が契約者となる場合でしたら、第三者による葬儀対応なども考慮しなければなりません。
そのような理由から任意後見契約を締結するには、契約される方の環境に応じて、下記の付随契約を合わせて結ぶ必要性が出てまいります。
■見守り委任契約
見守り委任契約は、主に将来型とされる任意後見契約においては必須の付随契約となりまして、文字通り【見守る】ことを業務とした契約となります。
将来型で契約を締結する場合は委任者の体力や判断能力が十分にある状態となりますので、任意後見契約(任意後見監督人を申請するまで)の効力が発動するまで長期間になる可能性があります。
その為、ご本人の状態を継続して確認させていただき、判断能力が低下したタイミングを見極めた段階で家庭裁判所に申立てを行うので、定期的な見守りが重要となる訳です。
特にお一人で暮らされている方の場合では見守り契約は重要で、判断能力が低下した状態を誰も気づかずに過ごされるということもありえますし、もし病気や怪我で動けなくなった状態になられていたら非常に危険です。
見守りの方法としては、定期的な訪問の他にも、電話での対応なども可能ですので、契約者ご本人の都合の良い方法を検討されれば宜しいかと思います。
親族ではなく、専門家などの第三者と任意後見契約を締結される場合は、必ず見守り契約を一緒に締結されることをお勧め致します。
尚、この見守り契約の期間は、契約者が決めた任意後見人が妥当な判断であったのかを検討出来る時間でもあります。
もし一度任せた任意後見受任者に不安を感じるようなことがあれば、委任契約を解除することも可能となりますので、大切な時期であるとお考えいただければ宜しいかと存じます。
参照:『任意後見契約の3つの契約形態とは?特徴と選び方を解説』
■財産管理委任契約
財産管理委任契約は、主に移行型契約の際に一緒に結ぶことが多いものです。
移行型契約の場合では判断能力は十分あるが体力的に心配がある際の契約形態となりして、支払いや金融機関への訪問などが困難な方には有用な契約になります。
又、例えば、施設への支払対応だけ、ですとか、銀行からの引き落とし対応のみ、のような限定した財産管理委任契約も可能となりますので、ご本人の状態に合わせて契約内容をご検討いただければ宜しいかと思います。
尚、財産管理委任契約では該当となる金融機関への説明も必要となります。金融機関によってはご本人の承諾が必要事項としているところもありますので、その場合は契約者ご本人にご同行いただいくなどの対応が必要となる場合もあります。
財産管理について実際には子供が管理している場合も多くあると思います。
しかしながら、判断能力が低下してしまった場合、大きな資金を動かすことは出来なくなり、金融機関から法定後見人を立てることを求められることも考えられます。
そのような状況にならないよう、任意後見契約と合わせた財産管理契約について改めてご検討いただくことは重要と考えております。
■死後事務委任契約
死後事務委任契約は、ご本人が亡くなられた後に効力を発生させる契約形態となります。
お亡くなりになる前に病院に入院されていたり、施設に入居していた場合では、最後の精算が発生します。又、葬儀の対応、納骨、遺品整理などもあり、それらの業務を引き受ける内容となります。
この契約では親族が任意後見人となる場合は不要になりますが、身寄りがない契約者の場合で、専門家などの第三者が任意後見人となる際には、亡くなられた後にどのような対応が必要となるのか解らないことが多いと思われますので契約締結は必須と考えて宜しいかと思います。
死後事務委任契約は遺言書で残せば良いのでは?とお考えになられる方もいらっしゃいますが、残念ながら、それは出来ません。
遺言書で法的に拘束できる事項は決まっていて、死後事務につきましては遺言書では遺せない為、死後事務委任契約を交わしておかなければなりません。
■遺言書で出来ること
①遺産相続に関する事項
②遺産の処分に関する事項
③身分上の事項
④遺言執行に関する事項 等
参考:『誰に必要? 死後事務委任契約で“安心できる人”とは』
■遺言執行(遺言書作成)
最近では遺言書の必要性についての認識が高まっており、遺言書を遺すことのハードルは低くなっているかと思います。
そして任意後見契約は公証役場で公正証書として作成しますので、一緒に公正証書遺言も作成されることが一般的となっているようです。
先程の死後事務委任契約とは異なり、法的に定められた事項を遺言書で遺すことになりますが、その中で遺言執行者を指定しておくことが可能です。
ご家族の中でどなたかがお亡くなりになった際に、相続対応が判らず、行政書士なども専門家に依頼することもあるかと思います。その対応先について遺言書の中で指示しておくというものになります。
遺言書では、必ずしも法定相続分で分ける必要はなく、ご自身のお考えで遺産分けを指示することが出来、その内容を遺言執行者は実行することになります。
任意後見契約を利用して老後を備えようと考えられる方にとっては、遺言書を遺すことは一連の流れになっているようです。
参照:『遺言書の作成を考えてみませんか? ~遺言書の種類~』
■家族信託
家族信託は、最近、注目を浴びている契約形態となります。
この契約では、指定した財産を信頼出来る人に預けることによって、その財産の管理・運用・処分といった事務を託すという契約になります。
この契約の一般的なもの体系として自益信託と呼ばれるものがありますが、この形態では委託者(委任者)が受益者となりますので、任意後見契約と合わせて運用することで非常に有益であると考えられています。
② 受託者に所有権を移して、管理・運用・処分を受託者が行う
③ 信託財産から生じた利益は受益者(委託者)の為に利用する
参考:『家族信託の仕組みとは?―相続で使える新しい選択肢-』
今回は任意後見の付随契約について触れさせていただきましたが如何でしたでしょうか。
任意後見制度はご本人が元気な時に結ぶ契約となりますので、それに付随した契約も併せて検討されることで、より安心した将来を迎えられると考えられております。
任意後見契約に関連した付随契約につきまして、詳細を確認されたいとのご希望がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
👇無料相談のお問合せはこちらから!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ