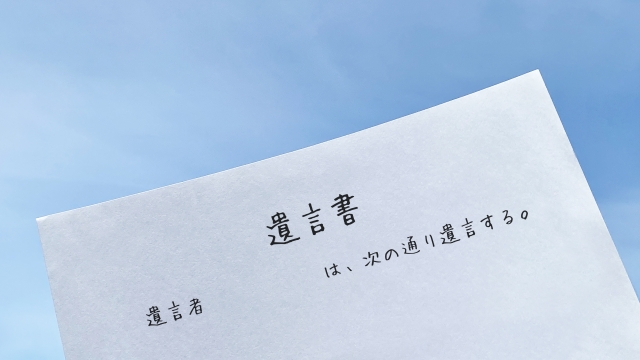.jpg)
こんにちは、行政書士の野口です。
今回は改めて、公正証書遺言について触れさせていただきます。
■公正証書遺言のメリット・デメリット
遺言書の全文を自身で書かなければならない自筆証書遺言と比較されるものとして公正証書遺言が一般の方にも広く知られております。
公正証書遺言は公証役場で作成されるもので、自筆証書遺言のように手軽に作成できるものにも関わらず、専門家の多くが公正証書遺言を勧めるのはどのような理由があるのでしょうか。
② 遺言者の遺言能力の有無で争われる可能性が低い
③ 家庭裁判所での検認を申請する必要がない
④ 公証役場で保管されるので紛失などの心配がない
⑤ 外出困難な遺言者の場合、公証人が出張して作成してもらえる
以上のように公正証書遺言では多くのメリットが存在しますが、自筆証書遺言と比べて遺言の確実性が高まることが最大のメリットではないでしょうか。
参考:『自筆証書遺言書保管制度の利用が増えてます~自筆証書遺言~』
では公正証書遺言でのデメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
② 遺言書の内容を気軽に変更できない
③ 2人以上の証人が必要
公証人が作成するために遺言の確実性は高まりますが、その分、費用が掛かるというデメリットが発生します。又、行政書士などの専門家に依頼する場合では、原文作成などの費用についても別途発生することになります。

■公正証書遺言の書き方
民法
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は公証人が作成しますので、高齢者でご自身での対応が難しい場合でも問題ありません。
作成された公正証書遺言を遺言者が確認して署名押印を行いますが、状況によっては公証人が代理で対応することも認められています。
下記が必要資料となりますが、各交渉役場で異なる指示を受ける場合もありますので、事前に確認されることをお勧め致します。
② 遺言者の戸籍謄本
③ 相続人の関係がわかる戸籍謄本
④ 不動産の登記簿謄本
⑤ 固定資産納税通知書、又は固定資産評価証明書
⑥ 預貯金のコピー等、財産の確認資料
⑦ 証人の身分証明書等の確認資料
■公証役場への手数料
下記が具体的な公証役場への手数料となりますのでご参照ください。
| 財産の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 13,000円 |
| 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 1億円以下 | 49,000円 |
※1億円を超える場合
3億円以下 49,000円+5,000万円毎に15,000円を加算
10億円以下 109,000円+5,000万円毎に13,000円を加算
10億円以上 291,000円+5,000万円毎に9,000円を加算
相続及び遺贈を受ける者が2人以ある場合、各相続人及び受遺者ごとに、その目的の価額によって手数料を算定し、それを合算した額となります。又、財産が1億円以下の場合は「遺言加算」として13,000円の手数料が加算されます。
尚、公証人の出張が必要となる場合は別途、日当、交通費が発生しますので各公証役場での確認が必要です。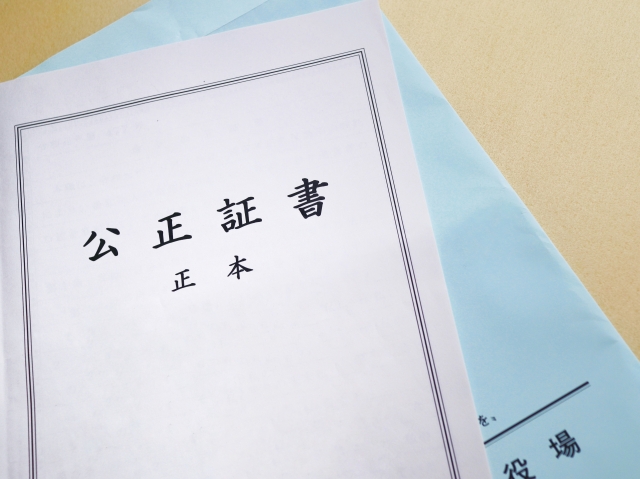
今回は、改めて公正証書遺言について触れさせていただきましたが如何でしょうか?
手数料がかかってしまうなどのデメリットもありますが、遺言を確実に実行させるという意味では公正証書遺言の作成をお勧めしたいところです。
専門家のサポートをご希望されるようでしたら、お近くの行政書士までお気軽にお問い合わせいただければと存じます。
👇無料相談のお問合せはこちらから!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ