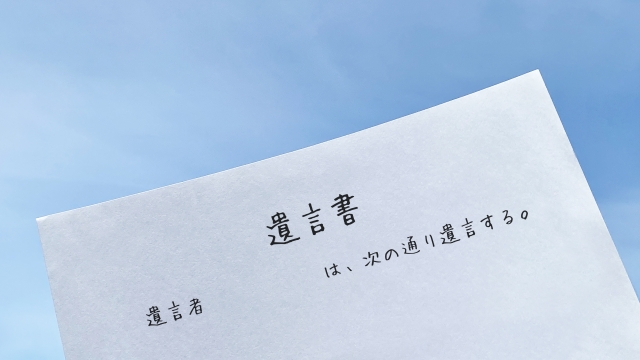.jpg)
こんにちは、行政書士の野口です。
今回は農地の相続手続きについて解説致します。
都市部から離れた場所での土地の相続においては、農地が相続対象となるケースも多いかと思います。しかしながら農地の相続では宅地とは異なる対応となりますのでご注意いただく必要があります。
農地の移転においては農地法によって厳しい制限が設けられおります。
■農地法とは
農地法
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
農地法は農業の生産性を維持する為に設定された法律となります。
その為、宅地のように売手と買手の合意によって所有権移転が出来るという訳ではありません。
農地の所有権を移転する場合では、農業委員会に許可をとる必要が出てきますので注意が必要です。
この制限は農地法3条によって規定されており、3条許可と呼ばれております。
又、農地を農地以外の使用目的に転用する場合では4条許可、転用を目的としての権利の移動については5条許可と呼ばれています。4条、5条許可につきましては別の機会での解説に譲らさせていただきます。
■農地法3条許可について
前述しましたように、農地の所有権を移転する場合は3条許可として農業委員会の許可を得る必要がありますが、実は、その許可要件は非常に厳しいものとなります。
① 全部効率利用要件
農地を効率よく耕作することが必要で労働力や機材などを含めて判断されることになります。
② 農地所有適格法人要件
法人の場合での要件となりますが「農地所有適格法人」であることが求められます。
③ 農作業常時従事要件
農作業を常時従事することが求められます。常時とは150日/年が目安となります。
④ 地域との調和要件
農作業を行うにおいて、地域の農業への取り組みに対し協力的でなければなりません。
*下限面積要件がありましたが、令和5年4月農地法改正により撤廃されています
以上のように、かなり厳しい条件が設けられております。
つまり、原則的に農家同士での所有権移転が前提となっている感じがしますね。
尚、3条許可を得ていない場合は、契約自体が無効となり、更に3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されてしまいます。
それでは相続の場合ではどうなるのでしょうか?
■農地の相続について
相続の場合では例外として、3条許可の取得は不要です。
農業委員会への届出は必要ですが、他の相続財産と同じ扱いとなります。
尚、相続を知った時から10か月以内に農業委員会まで届出をする必要があります。届出がされない場合、10万円以下の過料が課せられますので注意が必要です。
しかしながら、相続人が会社員の為、農地は不要となるケースも多いようですね。
その場合は農地転用や売却なども検討する必要もあるかと思います。
■包括遺贈と特定遺贈について
遺言を利用して包括遺贈と特定遺贈の方法から所有権移転をすることも可能となります。
包括遺贈とは全財産の割合で示すもので、特定遺贈とは特定の財産を指定する方法になりますが、いずれも遺言で残すということが必要になります。
ここで注意が必要ですが、特定遺贈の場合は相続人を対象にしなければなりません。
相続人以外への特定遺贈では3条許可を受けなければならなくなります。
参考:『遺産分割協議書は相続における合意の証になります』
今回は農地法3条許可を中心に農地の相続について解説させていただきました。
相続手続きにおいて農地が対象となることも少なくないかと思います。
農業委員会への届出など、通常の相続対応を異なる事項も発生しますので、不安に感じる事項などございましたら当事務所までご相談ください。
👇無料相談のお問合せはこちらから!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ