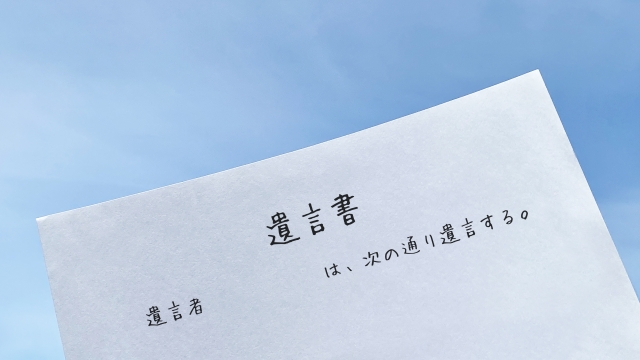.jpg)
こんにちは、行政書士の野口です。
2020年7月から自筆証書遺言書保管制度が施行されて、多くの方への認識が広まってきた為でしょうか?
最近ご質問をいただくことが多くなっております。
今回は改めて、自筆証書遺言について触れさせていただきます。
■自筆証書遺言のメリット・デメリット
以前、このブログでも遺言書の種類について解説させていただきましたが、自筆証書遺言は遺言書の中で最も気軽に作成できるものとして知られております。
参考:『遺言書の作成を考えてみませんか? ~遺言書の種類~』
自身で開催しているセミナーにおいても、自筆証書遺言のご質問を数多く受けますので、多くの方に広まっている印象が強いですね。
しかしながら、容易に作成できるメリットがありながら、少なからずデメリットも存在しておりますので作成にあたっては注意が必要となります。
要件を満たさない遺言書では遺言者の意思に反して無効となってしまいます。
自筆証書遺言のメリットは、やはり気軽に遺言書を遺すことが出来るということでしょう。
作成費用も掛かりませんし、お一人で文面を考えて遺しておくことも可能です。
① 基本的に紙とペンがあれば遺言書を遺すことが出来る。
② 公正証書遺言と違い、公証役場への手数料が不要(※保管制度を除く)
③ 遺言書の内容を他の人に知られないようにできる。
特にお子さんのいないご夫婦でしたら、簡易的で利用しやすい方法だと考えられています。
それでは逆にデメリットとしてはどのようなものあるでしょうか。
① 遺言書の全文を全て自筆で書かなければならない。
② 要件に則った記載でなければ無効となる可能性がある。
③ 家庭裁判所に検認の申請が必要(※法務局保管制度を除く)
④ 不利になる遺族から書き換えなどの恐れが発生する。
上記のように自筆証書遺言には多くのデメリットも挙げることになります。
特に全文を自筆で書かなければならないのは、遺言者が高齢者ということでしたら、かなりハードルが高い要件になるのではないでしょうか。
現在、財産目録についてはワープロ打ちでも可能とされてますが、それでも遺言書全文が自筆というのは大変な作業になると思われます。
又、遺した遺言書が有効に活用されないという致命的な危険性が潜在していることも忘れてはいけないですね。

■自筆証書遺言の書き方
民法
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言の書き方については民法で規定されております。
尚、繰り返しになりますが、財産目録についてはワープロ打ちでも問題ありません。
① 全文を遺言者が自書しなければならない
② 日付、氏名を自書して、押印をしなければならない
③ 財産目録を添付する場合は、目録に署名し押印しなければならない
④ 変更がある場合は変更箇所を示し、署名押印しなければならない
基本的な書き方に則ることも重要ですが、必要な署名、押印は忘れないようにしなければなりません。
他の注意事項としては、あやふやな表現はしないこと、相続財産の分配方法については明確しておくことが挙げられます。
尚、夫婦共同での遺言書や、ビデオで録画したものを遺言とすることも出来ませんので原則に則った書面での作成が必要となります。
■自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言では、不利になる遺族からの改ざんや紛失などのデメリットが指摘されておりますが、問題の解消を目的に、法務局による自筆証書遺言書保管制度が2020年7月より施行されております。
この制度は下記の特色を有していることから、ご利用される方が増えているようですね。
自筆証書遺言を検討されている方には、是非、お勧めしたい制度です。
① 法務局にて原本と画像データを長期保存してもらえる
② 保管の際には、自筆証書遺言の外形的な確認をしてもらえる
(*遺言書の内容についての有効性は保証されません)
③ 家庭裁判所の検認が不要となる
④ 相続開始後には証明書の発行や遺言書閲覧に対応してもらえる
⑤ 通知制度の利用で、確実に知らせてもらえる
⑥ 安価で利用できる(保管手数料3,900円)

今回は改めて自筆証書遺言について触れさせていただきましたが如何でしょうか?
自筆証書遺言は気軽に遺せる半面、多くの注意事項を確認する必要があります。
実際に要件が整わずに遺言書自体が無効とされてしまうケースも少なくありません。
私個人の意見ではありますが、自筆証書遺言ではなく、多少の作成手数料が発生するとしても公正証書遺言の作成をお勧めしております。当事務所では、遺言書は実現されなければ何もなりませんので、とお伝えすることにしております…
遺言書作成に関しましては、まずは専門家から話を聞かれることをお勧めいたします。内容によっては、遺言書作成に合わせて、より良い生前対策などもご提案できるかもしれません。
ぜひ、お気軽にご相談していただければと存じます。
👇無料相談のお問合せはこちら!
お問合せフォーム
行政書士 野口広事務所のホームページ